インプラントは、見た目も噛み心地も自分の歯のようで、「第二の永久歯」と呼ばれるほど満足度の高い治療といわれています。
しかし、毎日のセルフケアを怠ると「インプラント周囲炎」という炎症を起こすことがあります。
これは歯周病と同じように、細菌によって歯ぐきや骨に炎症を引き起こす病気で、放置するとせっかくのインプラントが抜けてしまうこともあります。
初期は出血や腫れといった軽い症状ですが、進行すると骨が溶けて治療が難しくなる場合があります。
そこで今回は、インプラント周囲炎の原因・症状・治療・予防法を中心に、日常生活で気をつけたいポイントを詳しく解説します。
インプラント周囲炎ってどんな病気?
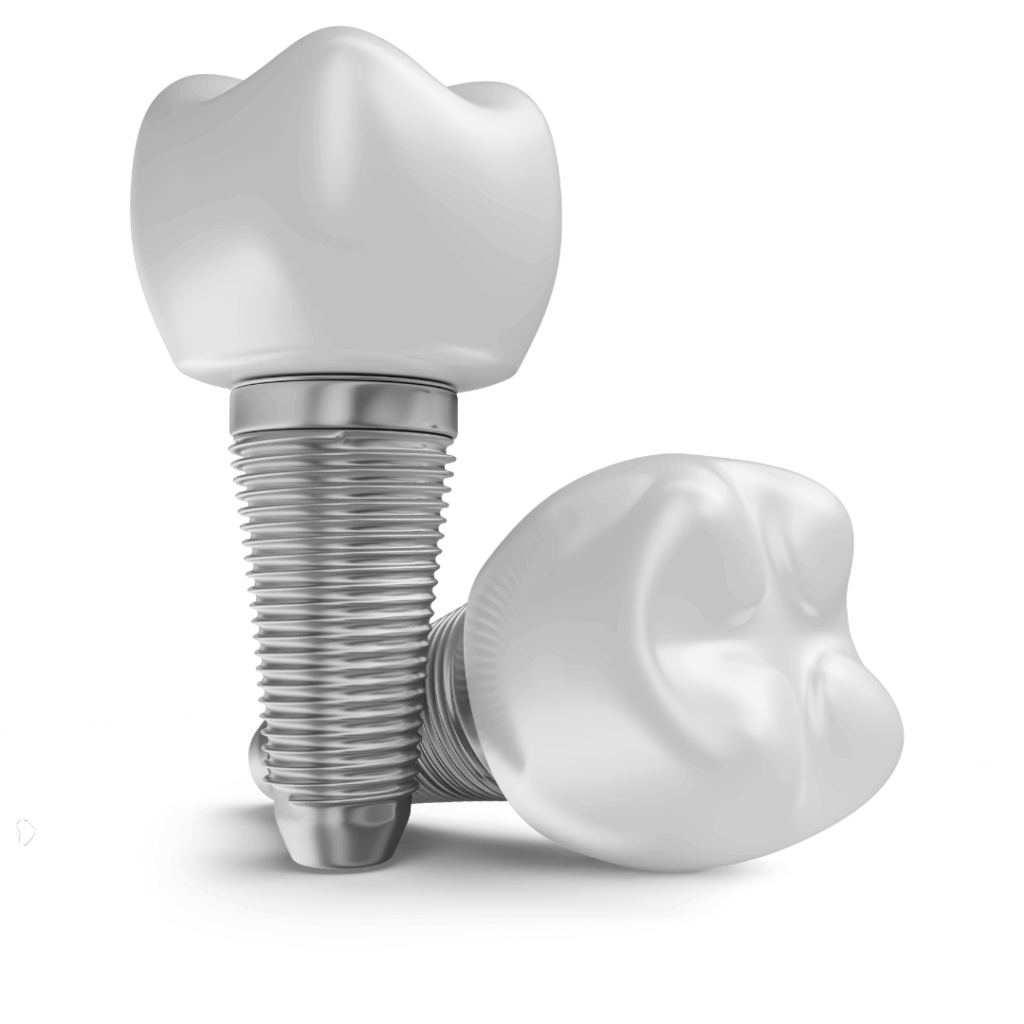
まず、「インプラント周囲炎」とはどのような病気なのかを確認しておきましょう。
インプラントを埋めた後、その周囲の歯ぐきやあごの骨に細菌が感染し、炎症が進行して骨が溶けてしまう状態です。
天然歯の「歯周病」に似ていますが、インプラントの場合は自覚症状が出にくく、進行が早いことが特徴です。
インプラントを長く安定させるためには、この「インプラント周囲炎」を起こさないこと、早めに見つけること、そして適切に治療することがとても大切です。
それでは、インプラント周囲炎の主な原因を見ていきましょう。
インプラント周囲炎の原因を知って防ごう
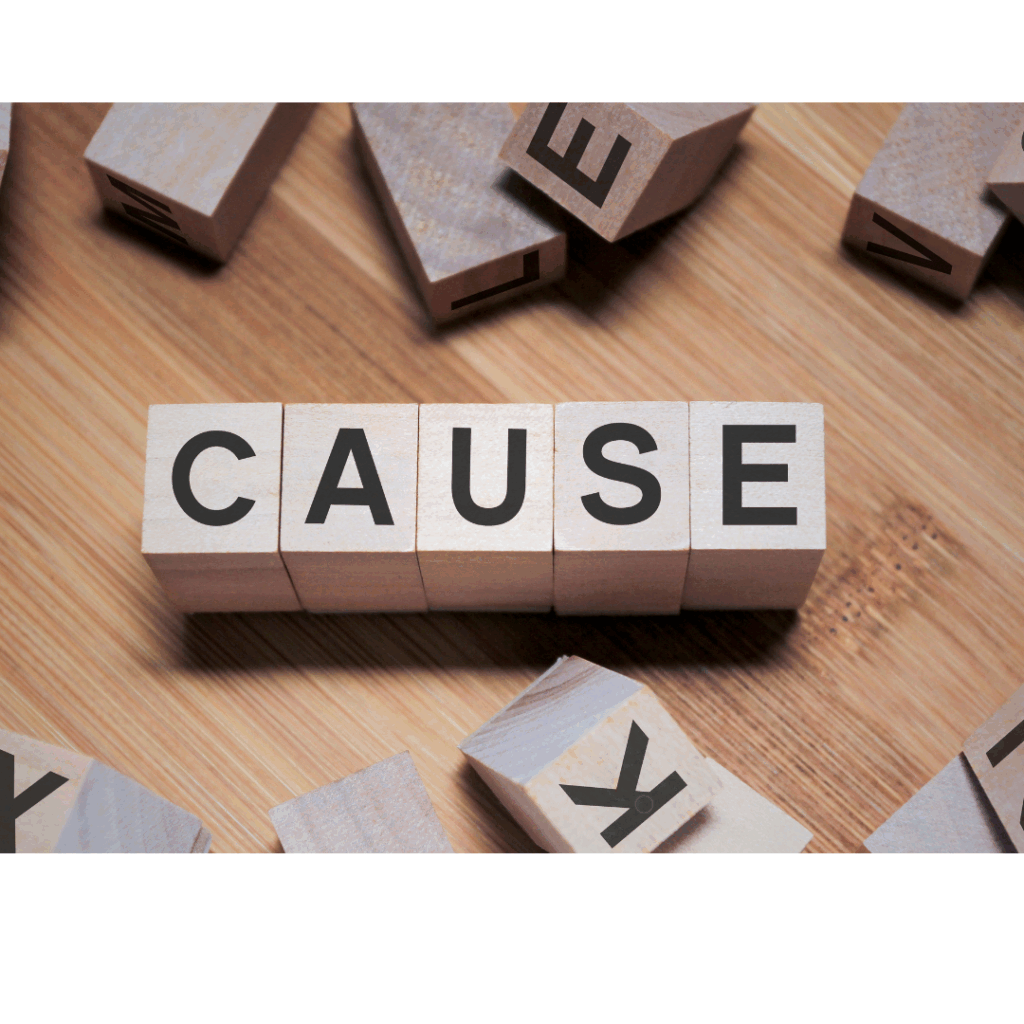
インプラント周囲炎が起こる要因には、いくつかの原因やリスク因子が関係しています。代表的なものをご紹介します。
口腔清掃が不十分な場合
インプラント周囲炎の大きな原因になる細菌は汚れの中にひそんでいます。
そのため、インプラントのまわりにプラーク(細菌のかたまり)が付着したままだと、炎症を引き起こす原因になります。
歯周病の既往歴がある場合
天然歯で歯周病になった経験がある方や歯を失った原因が歯周病の方は、インプラント周囲炎を発症するリスクが高いといわれています。
全身疾患の影響
糖尿病や免疫力の低下、貧血などがあると、組織の治りが悪くなり、感染への抵抗力も下がり、インプラント周囲炎のリスクが高くなります。
喫煙や不規則な生活習慣
喫煙は歯ぐきの血流を悪くし、だ液も減少するため、細菌に対する防御力を低下させます。
睡眠不足や偏った食生活などの不規則な生活も炎症のリスクを高めます。
定期メンテナンスの不足
定期的な検診やクリーニングを怠ると、トラブルの早期発見が難しくなり、症状が悪化してしまうことがあります。
強い咬みしめ・歯ぎしり
インプラントに過度な力がかかると、周囲の骨や歯ぐきにストレスがかかり、炎症を引き起こすことがあります。
これらがいくつか関係して作用することで、インプラント周囲炎の発症・進行につながる場合があります。
インプラント周囲炎の症状とは?

インプラント周囲炎は、初期のうちは痛みや違和感などの自覚症状が少ないことが多く、「気づいたときには炎症が進行していた」というケースも少なくありません。
代表的な症状は次の通りです。
歯ぐきの赤み・腫れ
健康なピンク色の歯ぐきが赤くなったり、腫れぼったく見えたりします。
出血
歯みがきやフロス、歯間ブラシを使ったときに少し触っただけで、出血が見られることがあります。
歯ぐきが下がる
炎症が進行すると歯ぐきが下がり、被せ物が合わなくなったり、インプラントの金属部分が見えたりしてくることもあります。
口臭
細菌、出血、膿などがあることで、口臭が強くなる場合があります。
インプラントのぐらつき・違和感
骨が溶けて支えが弱くなると、インプラントが動いたり、噛んだときに違和感を覚えたりするようになります。
このような症状を放置すると、治療が難しくなったり、追加の処置が必要になって費用が増える場合もあります。
インプラント周囲炎を放置したときのリスク

インプラント周囲炎をそのまま放置すると、次のような深刻なトラブルにつながるおそれがあります。
・顎の骨が溶ける
炎症が進行すると、インプラントを支えている骨が少しずつ吸収され、土台が弱くなり安定感が少なくなります。
・インプラントが抜けて落ちてしまう
骨の支えを失うと、最終的にインプラントが動揺したり、最悪の場合、抜け落ちてしまったりすることもあります。
・全身への悪影響
炎症が強くなり、口の中の細菌が血流に入り込むと、全身をめぐり、糖尿病や心疾患など、全身の健康にも悪い影響を及ぼす可能性があります。
・治療期間・費用の増加
症状が進行していると、外科的な処置や骨再生治療が必要になり、その分治療期間や費用が増加する傾向があります。
このように、インプラント周囲炎は「早期発見・早期対応」大切です。
早めに対応することで、進行を防ぎ、インプラントを良い状態で維持することにつながります。
そのため、少しでも異変を感じたら、自己判断せずに歯科医院を受診しましょう。
メンテナンスはインプラントを長持ちさせるための習慣と定期ケア

インプラントを長く快適に使い続けるためには、メンテナンスが大切です。
治療が終わって「もう大丈夫」と油断してしまうと、プラークが溜まり、インプラント周囲炎を引き起こす原因となります。
ここでは、患者さんご自身が行う「日常のセルフケア」と、歯科医院で受ける「定期的なプロフェッショナルケア」に分けて詳しくご紹介します。
ご自宅でできる毎日の予防法
インプラントの周りは、天然歯と違ってクッションの役割をする歯根膜が存在しないため、炎症が起きると進行が早い傾向があります。
そのため、毎日の丁寧なセルフケアが重要です。
・丁寧な歯磨きと補助清掃用具の活用
インプラントの周囲にはプラークが付着しやすいため、毎食後のブラッシングが大切です。
歯ブラシはやわらかめの毛を選び、インプラントと歯ぐきの境目を細かく磨きましょう。さらに、歯間ブラシ・デンタルフロス・スーパーフロスなどの補助清掃具を併用することで、細部の汚れまで効果的に除去できます。
・歯ぐきの健康チェック
歯ぐきの色や腫れ、出血の有無を毎日の歯磨き中に観察する習慣をつけましょう。
「出血」「腫れ」「違和感」などのサインは、インプラント周囲炎の初期症状である可能性があります。
早めに気づくことで、炎症の悪化を防ぐことができます。
・生活習慣の見直し
インプラント周囲炎の発症には、生活習慣の影響も大きく関係します。
タバコの中に含まれるニコチンは、歯ぐきの血流を悪化させ、細菌への抵抗力を低下させます。
また、食いしばりや歯ぎしりのある方は、ナイトガード(就寝時マウスピース)を併用して、インプラントにかかる力を分散させることが負担を軽減します。
飲酒の習慣や睡眠不足、ストレスなども、免疫力が低下するため、炎症のリスクを高める要因です。
日常生活を整えることが、より良い予防策といえるでしょう。
歯科医院での定期メンテナンス
セルフケアだけでは、どうしても落としきれない汚れやバイオフィルムが残りがちです。そのため、歯科医院での定期メンテナンスで、お口の中を清潔にして維持する様にしましょう。
・定期検診の目安
インプラント治療後は、3〜6か月に1回の定期チェックが理想的です。
お口の状況に合わせて歯科医師が定期検診の時期をご案内します。
特に、喫煙者や糖尿病のある方、過去に歯周病を患った方は、より短い間隔(2〜3か月ごと)が望ましいとされています。
歯科医師や歯科衛生士が、インプラント周囲の歯ぐきや骨の状態を細かく確認します。
・主な検査内容
レントゲン撮影
骨吸収やインプラント体周囲の炎症の有無を確認。
歯周ポケット検査
歯ぐきの炎症や出血の程度をチェックします。
咬み合わせの確認
咬む力のバランスを調整し、インプラントへの負担を軽減します。
クリーニング
専門の器具を使い、歯面やインプラント周囲に付着したバイオフィルムも除去します。
見た目をきれいにするだけでなく、炎症を防ぐためにも大切な処置です。
専用のチタンやプラスチック製チップを用いることで、インプラント表面を傷つけずに清掃が行えます。
インプラント周囲炎の治療方法

インプラント周囲炎の治療法は、炎症の進行度・骨の吸収状態・全身の健康状態などによって異なります。
大きく分けると「非外科的治療」と「外科的治療」の2つの方法があります。
・非外科的治療方法(初期~中程度)
炎症が比較的軽く、骨の吸収が少ない段階では、次のような処置を行います。
歯石・プラークの除去
専用の器具を使い、インプラント周囲の歯石や細菌のかたまりを取り除きます。
歯周ポケット内の洗浄
感染している部分を洗浄し、抗菌薬や消毒薬で炎症を抑えます。
口腔衛生指導と生活習慣の改善
再発を防ぐために、正しいブラッシング方法の確認や生活習慣の見直しを行います。
・外科的治療方法(重度)
骨の吸収が進んでいたり、非外科的治療で改善が見られない場合は、外科的な処置が検討されます。
フラップ手術
歯ぐきを開いて感染組織を除去し、インプラントの表面を清掃します。
状態によっては、必要に応じて骨の形態を整えます。
骨再生療法(GBRなど)
失われた骨の再生を促し、インプラントの支えになる顎の骨を回復させる治療です。
レーザー治療
レーザーを用いて殺菌を行い、炎症の軽減を期待します。
インプラント除去
骨がほとんど残っていない場合は、いったん除去し、治癒後に再治療を検討します。
どの治療法も、早い段階で対応することでインプラントを残せる可能性が高くなります。
インプラント周囲炎の予防法のポイント
インプラント周囲炎を防ぐためには、症状が出てから治療するのではなく、日頃から予防を意識することが重要です。
以下のポイントを押さえて、長く健康な状態を保ちましょう。
・毎日の丁寧なセルフケア
プラークをためないことが大切です。
歯ブラシにだけではなく、歯間ブラシやデンタルフロス、洗口液などを組み合わせて清掃しましょう。
・定期的な歯科メンテナンス
3〜6か月に1回は歯科医院でチェックとクリーニングを受け、早い段階で異常を見逃さないようにします。
・リスク因子の管理
喫煙・糖尿病・歯周病・歯ぎしり・食いしばりなどは炎症を悪化させる原因となります。必要に応じて医師や歯科医師のサポートを受けましょう。
・日々のセルフチェック
歯ぐきの赤み・腫れ・出血・口臭・違和感などのサインを見逃さず、気になる症状があれば早めに受診しましょう。
毎日のケアと定期的なメンテナンスを組み合わせることで、インプラントを長持ちさせることが見込めます。
インプラント周囲炎を防ぐための生活習慣の見直し

喫煙習慣を見直す
たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素は、歯ぐきの血流を悪化させ、酸素や栄養を十分に届けにくくします。
そのため、インプラント周囲の組織が治りにくくなり、感染や炎症が進みやすくなります。また、喫煙者は顎の骨とインプラントの定着が良くないなど、インプラントの成功率が低いことも報告されています。
禁煙が難しい場合は、少しずつ本数を減らすことから始めてみましょう。
歯ぎしり・食いしばりに注意する
寝ている間や集中しているときに歯ぎしりや食いしばりをしていると、インプラントに過剰な力が継続的にかかり、周囲の骨や歯ぐきにダメージを与えます。
症状がある方は、歯科でマウスピース(ナイトガード)を作製し、力の負担を軽減するのがおすすめです。
正しいブラッシング習慣を継続する
インプラントを入れた後も、毎日の歯みがきがとても大切です。
歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスを使って細かい部分まで清掃しましょう。
また、歯科医院で正しいブラッシング方法を定期的にチェックしてもらうことで、磨き残しを予防しやすくなります。
全身の健康を整える
糖尿病・貧血・免疫力の低下などは、歯ぐきの抵抗力を弱め、感染への防御力を下げます。特に糖尿病は歯周病菌との相互関係があるため、血糖値が高い状態が続くと傷の治りが悪くなり、歯ぐきの炎症を起こしやすくなります。
定期的な健康診断や内科での管理を続け、全身の健康状態を把握しておきましょう。
栄養・休息・ストレスケアを大切に
体の治癒力を支えるのは、バランスのとれた食事と十分な睡眠です。
タンパク質・ビタミンC・鉄分などは、歯ぐきの修復の大切な成分です。
また、ストレスは免疫力を下げるため、リラックスする時間を意識的に作ることも重要です。
このように、日々の習慣を少し意識するだけで、インプラント周囲炎のリスクは軽減します。
「治療後も生活習慣の中でケアを続けること」こそが、インプラントを長持ちさせるポイントです。
毎日のケアと定期検診で、インプラントを維持しましょう
「インプラント周囲炎」は、インプラント治療後に起こる可能性のあるトラブルのひとつです。
しかし、原因を理解し、毎日のケアと定期的なメンテナンスを続けることで、多くのケースは予防できます。
もし炎症や出血などの症状が出ても、早めに受診して適切な治療を行えば、インプラントを維持できる可能性は十分にあります。
お口の中を清潔に保ち、定期的にメンテナンスに通うことが大切です。
また、日常生活の見直しで免疫力を高めましょう。
インプラント治療を受けた方は「予防と早期対応が重要」ということです。
不安な症状やお手入れ方法については、歯科医院に早めに相談するようにしましょう。

