インプラント治療を検討される患者様から「口の中に硬いこぶのようなものがある」といったご相談をいただくことがあります。
診察の結果、その原因としてよく見られるのが「下顎隆起(かがくりゅうき)」です。
特に、日常生活でのストレスや、睡眠中・日中に無意識に行っている「歯ぎしり・食いしばり」が、下顎隆起の発生や増加に関係していると考えられています。
そこで今回は、下顎隆起が「なぜ起こるのか」「どのように対応すべきか」を詳しく解説いたします。
下顎隆起とは?症状と特徴について

「下顎隆起」とは、下あごの内側(舌側部分)にある骨が過剰に発達し、こぶのように盛り上がった状態を指します。
医学的には「骨隆起」の一種で、上あごの中央にできる「口蓋隆起」などと同じように、あごの骨の一部分が少しずつ盛り上がって「こぶ」のようになる状態です。
主な特徴としては、以下のような点が挙げられます。
・一度できると自然に小さくなることは少なく、刺激が続くと徐々に大きくなる傾向がある
・痛み・腫れ・赤みなどの炎症症状はほとんどない
・触ると硬く、骨のように感じる
インプラント治療を検討している方の場合、このような骨の突出は「義歯やブリッジの装着」「インプラント埋入時の手術」「義歯使用時の違和感」などに影響することがあります。そのため、歯科医院で早期に発見し、必要に応じて適切な処置を行うことが大切です。
下顎隆起が増えた理由とは?歯ぎしり・ストレスとの深い関係
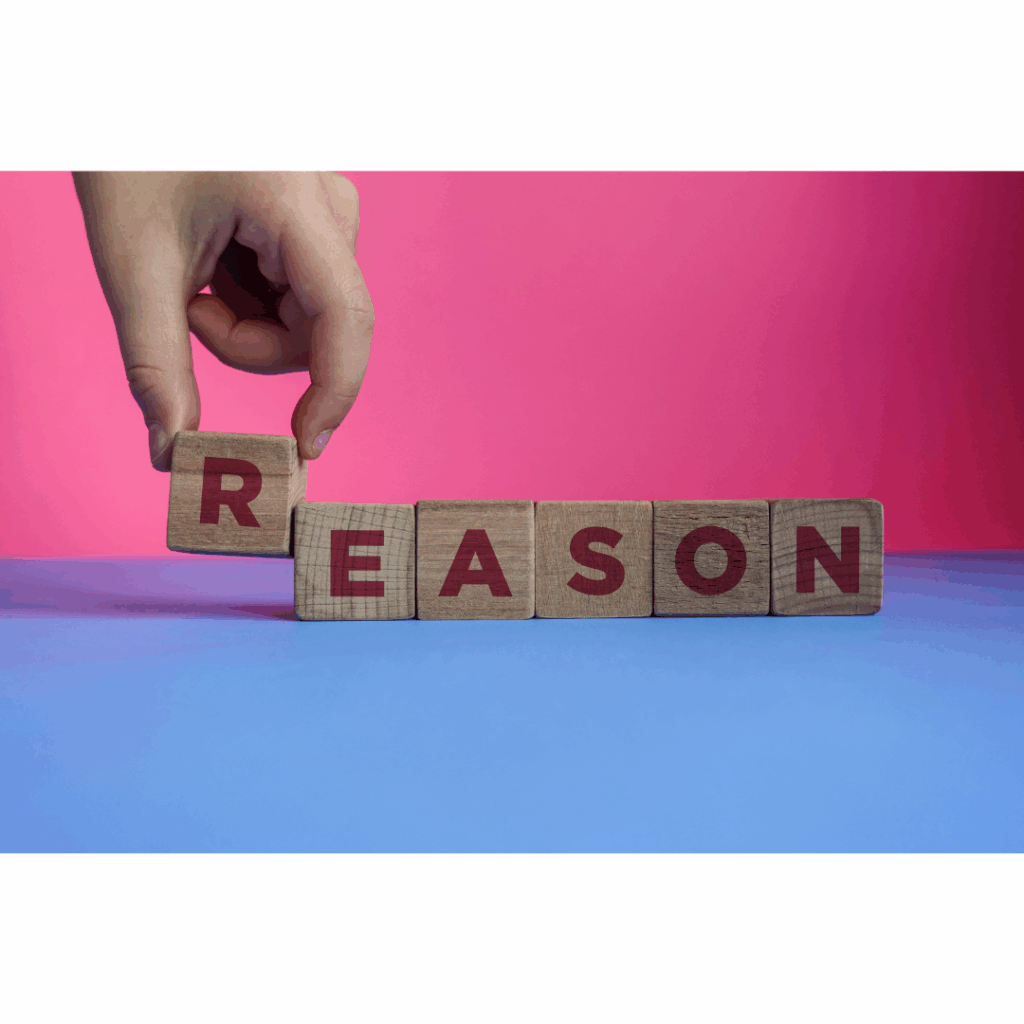
歯ぎしり・食いしばりがあごの骨を変化させる理由とは
下顎隆起ができる背景には、「顎や歯に強い力が何度もかかること」が関係しています。
たとえば、寝ている間の歯ぎしりや、日中の無意識な食いしばり(クレンチング)、さらには上下の歯が軽く接触し続けるTCH(歯列接触癖)などが関係しています。
このような動作によって歯やあごの骨に大きな負担がかかる機会が多いと、体はその力に適応しようとして骨を厚くしようと反応します。
その結果、骨が少しずつ盛り上がり、「こぶ」のような形で現れると考えられ
ています。
具体的な例をご紹介します。
・就寝中に歯を強くこすり合わせたり(グラインディング)・噛みしめたり(クレンチング)することで、奥歯を支える下あごの内側に圧力が加わる。
・この刺激が長い間続くと、骨の代謝が活発になり、骨が厚くなったり盛り上がったりする可能性があります。
・その結果、舌側(内側)や奥歯の近くの骨に「下顎隆起」ができやすくなります。
日常的な噛む力のクセが継続すると、下顎隆起を引き起こすきっかけになることがあります。
ストレスとの関係
歯ぎしりや食いしばりの背景には、ストレスが深く関係していると考えられています。
ストレスを感じると自律神経のうち「交感神経」が活発になり、筋緊張しやすくなります。あごの筋肉(咀嚼筋)もその影響を受け、無意識のうちに噛みしめる力が強くなってしまうことがあります。
そうすると、「ストレス→筋肉の緊張→食いしばり・歯ぎしり→顎への負担→骨が発達」という流れになります。
そして、その結果が下顎隆起の一因になると考えられています。
そのため、歯科医院では「ストレス緩和・睡眠の質の改善・マウスピースの活用による力の分散」などを併せて提案することがあります。
下顎隆起が増えた理由
近年、歯ぎしりや食いしばりの自覚症状がある方、または顎に力が入りやすい生活をしている人が増えているといわれています。
その背景には、次のような要因が考えられます。
・スマートフォンやパソコンの長時間使用により、首やあごに負担のかかる姿勢が続く傾向がある。
・睡眠の質の低下やストレスの増加で、寝ている間に歯ぎしり・クレンチングが起こりやすくなる。
・噛み合わせの変化や、硬いものを好む食生活によって咬合圧が強くなる
・高齢化に伴い、義歯やインプラントなど口腔内の変化に意識が向くようになったため。
これらの要因から、下顎隆起に気づく方が増えているといわれています。
「あごの内側に違和感がある」「マウスピースが骨に当たる」といったご相談が増加傾向になっており、生活習慣やストレスとの関係を一緒に見直すケースが増えています。
下顎隆起で起こる問題と対処法とは

下顎隆起は多くの場合、痛みや炎症を伴わず、病気としての治療を必要としないことが多いでしょう。
そのため放置されやすいものの、「全く影響がない」というわけではありません。
それでは、下顎隆起が関係する代表的な問題点をご紹介します。
義歯・インプラント・被せ物(補綴)への影響
下顎隆起はさまざまな治療を行う上で影響を及ぼすことがあります。
義歯(入れ歯)
下あごの内側に隆起があると、義歯の適合が悪くなり、痛み・違和感・装着の不安定さを引き起こすことがあります。
インプラント治療
下顎骨の形態が複雑になることで、インプラントの埋入位置や角度、手術のアプローチ方法に工夫が必要となるケースがあります。
被せ物(クラウン・ブリッジ)
歯ぎしりや食いしばりがあると、被せ物の破損や脱離、骨への過剰な負担を招くことがあります。
特にインプラントは天然歯のような「歯根膜のクッション」がないため、力の影響を受けやすく注意が必要です。
食事・発音・お口の中の違和感
下顎隆起が大きくなると、食事の際に当たる、こすれる様な違和感を覚える場合や、硬いものを噛むと軽い痛みが出たりすることがあります。
また、義歯を使っている場合は装着感が悪くなり、顎の粘膜部分に刺激が加わって口内炎や傷を起こしやすくなります。
さらに、骨のこぶが大きいと舌の動きが制限されたり、発音・清掃の際に違和感を覚えたりすることもあります。
見えないストレス・心理的な負担
「口の中にこぶのようなものがある」ということが不安やストレスの原因になることがあります。
中には「腫瘍かもしれない」と心配される方も多く、受診までに不安を抱えてしまうケースもあります。
また、歯ぎしり・食いしばりなどが原因とわかると、「インプラントを入れても大丈夫?」「また悪化しないだろうか」と心配される方もいます。
当院では、こうしたお悩みや不安などのサポートも行っていますので、ご安心ください。
下顎隆起の対処法と治療の選択肢

下顎隆起が見つかった場合、どのように対処すればよいか不安な方もいると思います。
特にインプラント治療を予定している方は、「日常生活の力のコントロール」がとても重要です。
それでは、段階的な対応方法をご紹介します。
マウスピース(ナイトガード)の装着
睡眠中の歯ぎしり・食いしばりの可能性がある場合は、オーダーメイドのマウスピースを作製します。
上下の歯が直接当たらない様にし、顎や被せ物にかかる力を分散して負担を軽減します。
咬み合わせや被せ物のチェック
咬み合わせのバランスや、クラウン・ブリッジ・インプラントの被せ物に問題がないかを確認します。
部分的に特定の歯だけに強い力が集中している場合は、調整が必要です。
日常生活の姿勢やストレスの見直し
スマートフォンやパソコン作業で頭が前傾していると、顎の周りの筋肉が緊張します。
姿勢を整えることだけでなく、リラックスした状態を保つことが大切です。
また、「上下の歯を離す時間を意識する」「食事や会話以外では歯を接触させない」など、歯の安静位を意識することも効果的です。
それ以外に十分な睡眠とストレスケアも、歯ぎしりや食いしばりの軽減につながります。
外科手術(下顎隆起の切除)
日常生活や入れ歯の使用に支障がある場合、またはインプラント手術に影響するほど大きい場合には、外科的切除を検討します。
手術は局所麻酔下で行い、隆起部分の骨を削り整える処置です。
手術後の回復は比較的良好で、保険適用となるケースも多く見られます。
ただし、切除しても、原因である歯ぎしりや食いしばりが改善されなければ再発の可能性があります。
インプラント治療における考慮点
インプラントを検討する際は、下顎隆起の有無や位置を事前に的確に把握しておくことが重要です。
・CTなどの立体的な画像で骨の形態や厚みを確認する
・術前・術後の歯ぎしり対策を行い、被せ物への力を分散する
・隆起に近い部位へ埋入する場合は、骨の強度や血流、清掃性を考慮して治療計画を立案する
下顎隆起を予防するためにできる「毎日のケアと生活習慣」

「下顎隆起を完全に予防する」ことは難しいものの、発症や進行を抑える生活習慣を意
識することで、インプラントやお口の健康を維持することが可能です。
日常の中で実践できるポイントを紹介します。
無意識の食いしばりを予防するリラックス習慣
日中、無意識に歯を噛みしめていたり、軽く接触させていたりする方は少なくありません。
そんな方は、意識して「歯を休ませる時間」を作ることが大切です。
・食事や会話以外では、奥歯を軽く離した「リラックスした状態」を意識する
・作業の合間に「歯が当たっていないか?」と確認し、気づいたら歯を離す
・スマホやパソコン作業時は、頭が前に出たり、肩に力が入っていたりしないか姿勢をチェックする
このようなちょっとした意識づけが、顎への負担軽減につながります。
・日常生活の睡眠とストレス管理を整える
毎日のストレスや疲労は、歯ぎしりや食いしばりは下顎隆起の大きな原因になります。
日常生活の中で「緊張をほどく時間」を意識的に作りましょう。
・適度な運動や趣味の時間を取り入れ、ストレスを溜めにくい環境をつくる
・就寝前にストレッチ、温かい飲み物などでリラックスする
・就寝中の歯ぎしり対策として、マウスピース(ナイトガード)の装着も効果が見込めます
咬み合わせ・補綴物の定期チェック
被せ物や入れ歯、インプラントの被せ物は、経年変化によって微妙にズレたり摩耗した
りすることがあります。
定期的なチェックで、咬み合わせのバランスを保ちましょう。
・咬み合わせに違和感がある、顎が疲れる、痛む場合は早めに受診をしましょう
・入れ歯が動く、当たるといった症状も、放置しないで歯科医院で調整しましょう
・インプラント治療を受けている方は、骨の状態や歯ぎしりの習慣を含めたメンテナンスを歯科医院と共有する
定期的なメンテナンスが、インプラントや被せ物の維持につながります。
片側噛み・硬い食べ物を控える
食事のとき、どちらか一方ばかりで噛むクセや、硬い食べ物ばかりを選ぶ習慣は、特定
の顎の部位に過度な負担をかけてしまう可能性があります。
左右両側をバランスよく使って噛むように意識する、ナッツやスルメ、氷など硬い食品の
摂取を控えるなどの工夫をしましょう。
また、調理方法で咀嚼負担を軽減する工夫を取り入れることも有効です。
このような小さな工夫が、日常生活の負担を減らし、下顎隆起の悪化を防ぐ効果が見込め
ます。
インプラント治療を見据えた下顎隆起への対処法のポイント

当院では、インプラント治療を検討される患者様に対し、下顎隆起の有無やその影響を丁
寧に評価し、治療計画に反映することを大切にしています。
当院で実施している主な対応の流れをご紹介します。
初診・検査でのチェックポイント
口腔内の確認
下あごの内側(舌側・奥歯の付近)に、硬い隆起がないかを丁寧に触診します。
CT・パノラマ撮影
顎骨の形状や厚み、下顎隆起の位置とインプラント予定部位との関係を立体的に把握しま
す。
歯ぎしりや食いしばりの有無
問診や生活習慣のヒアリングを行い、必要に応じてナイトガード(マウスピース)の使用
を提案します。
咬み合わせ・被せ物の確認
過去に被せ物の破損や入れ歯の不具合がなかったか、また日常生活や睡眠中の噛みしめの
傾向を確認します。
治療計画・カウンセリング時の説明
軽度の下顎隆起の場合
機能や見た目に問題がなく、インプラント設計上も支障がないと判断される場合は、マウ
スピースの使用や噛みしめの改善指導を優先します。
隆起が大きい場合
義歯の適合やインプラント埋入に支障をきたすと判断された場合は、外科的切除を含む治
療計画をご提案する場合があります。
長期的なリスクの説明
歯ぎしり・食いしばりを放置したままインプラントを入れると、上部構造の破損・顎骨の
再変形・義歯のずれなどのトラブルが起こる可能性があるため、十分な説明と対策を行い
ます。
術後の長期的なメンテナンス
マウスピースの継続使用
インプラントを支える骨への負担を減らすため、術後もナイトガードを継続的に使用し、噛みしめの力を分散します。
定期的なチェック
インプラント部位だけでなく、顎骨や下顎隆起部の変化、義歯との接触部位のトラブルなども含めて確認します。
インプラントをするなら下顎隆起・日常の習癖・力のコントロール
下顎隆起は痛みなどが少ないため気づかれにくいですが、インプラント治療では見逃せないポイントです。
歯ぎしりや食いしばり、ストレスによる強い力が顎にかかることで、下顎隆起が出来たり大きくなったりすることがあります。
インプラントを長く安定させるには、マウスピースで力を分散する、噛みしめの習慣を改
善する、咬み合わせを整えることが大切です。
当院では、インプラントをご希望の方に顎骨の状態・歯ぎしり習慣・咬み合わせを丁寧に
確認し、必要に応じてマウスピース・調整・手術を含めたより良いプランをご提案いたし
ます。
「口の中のこぶが気になる」「歯ぎしりを指摘された」「インプラントが心配」という方は、
ぜひ一度ご相談ください。


