「インプラント治療を希望しているけれど、金属アレルギーが心配……。」
そんな不安をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
インプラントに使われる金属は、主にチタンが使用されています。
生体との相性が良いため、医科では心臓ペースメーカーや人工関節などに使用されています。
ただし、まれなケースではありますが、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。
アレルギー反応として、口腔扁平苔癬(こうくうへんぺいたいせん)や掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)などが現れる可能性があります。
そこで今回は、インプラントと金属アレルギーの関係、チタンやジルコニアなど素材の違い、そして事前にできるアレルギー検査について詳しく解説します。
インプラントに使われる代表的な素材とチタンの特徴

・チタンの特徴
チタンは高い生体親和性と強度を持ち、現在のインプラント治療で広く使用されている素材です。
チタンが選ばれる理由をご紹介します。
・身体とのなじみが良く、生体親和性が高い
・表面に保護膜ができて、金属が体に溶け出しにくくなる
・強度や耐久性も優れており、しっかり噛んでも壊れにくい、高い強度があります。
また、チタンは他の金属(ニッケル、コバルト、クロムなど)と比べてアレルギーリスクが低いとされます。
しかし、金属のため、金属アレルギーのリスクが全くないわけではありません。
さらに、チタンインプラントといっても「チタ100%」ではなく、強度や加工性を高めるために他の金属を添加することがあります。
そのため、合金成分に金属アレルギーを引き起こす成分が含まれていると、アレルギーリスクが高くなる可能性があります。
また、インプラント手術中やインプラント周囲炎などで表面が摩耗・破損し、金属片やイオンが溶けだすことでアレルギー誘発の可能性が考えられます。
そのため、チタンは非常に身体となじみやすいとされる素材ですが、リスクがゼロではありません。
チタンアレルギーの心配はある?発症のリスクをわかりやすく解説

・発症頻度はどの程度?
チタンによるアレルギー反応は非常の少なく、まれなケースです。
多くのインプラントを専門に治療している歯科医院でも、「金属アレルギーがあってもインプラント治療は可能」という認識が一般的で、その理由としてチタンの低アレルギー性が挙げられます。
ただし、金属アレルギーの方の心配な方は、事前にアレルギー検査をすることでリスクを確認出来ます。
・なぜ起こる?チタンアレルギーが発生する仕組み
金属アレルギーは、主に「遅延型アレルギー」と呼ばれるタイプです。
これは、すぐに症状出るのではなく、金属から溶け出した微量なイオンが体のたんぱく質と結びつき、体が“異物”と判断してしまうことで起こります。
その結果、免疫細胞が反応して炎症を引き起こすのですが、この反応はすぐに出るわけではありません。
症状が出るまでに数週間から数ヶ月、場合によってはもっと長くかかることもあります。
そのため、原因の特定に時間がかかることがあり、歯科では昔入れた銀歯が原因で金属アレルギーを引き起こすケースが分かっています。
金属アレルギーで起こりやすい症状の口腔扁平苔癬と掌蹠膿疱症
歯科用金属でアレルギー反応が出やすいのは、保険適用ができる銀歯が多いですが、歯科金属がアレルギーの原因となる場合、次のような症状が報告されています。
・口腔扁平苔癬とは
口腔扁平苔癬とは、口の粘膜(舌・頬の内側・歯ぐきなど)に炎症や白いレース状の模様が現れる病気です。
粘膜がざらついたり、ただれ(びらん)を伴ったりすることもあります。
主な自覚症状には下記のようなものがあります。
・粘膜の赤みや腫れ
・しみる・ヒリヒリする痛み
・味覚の異常
・粘膜の違和感
インプラント治療後、これまで見られなかった口内の異常や痛みが突然現れた場合は、
金属アレルギーが関係した口腔扁平苔癬の可能性も考えられます。
・掌蹠膿疱症とは
掌蹠膿疱症は、手のひらや足の裏に小さな水ぶくれができる皮膚の疾患です。
症状は、かゆみや痛みを伴うこともあり、繰り返し発症することがあります。
インプラント金属が原因となる場合、掌蹠膿疱症の発症や悪化と関連づけられた報告がまれにあります。
実際に、歯科金属やインプラントを除去したことで皮膚症状が落ち着いた例も確認されています。
また、皮膚症状と口腔の粘膜症状(口腔扁平苔癬など)が併発するケースもあり、そのような場合は金属アレルギーとの関連を疑う必要があります。
チタンアレルギー検査(パッチテスト・血液検査など)

金属アレルギーが心配な方は、インプラント治療前に以下のような金属アレルギー検査を受けることができます。
治療前に検査を行っておくことで、金属アレルギーのリスクを減らすことができます。
・パッチテスト
パッチテストとは、アレルギーの原因の可能性のある物質(アレルゲン)を皮膚に少量貼り付けて反応を確認する検査です。
皮膚(背中や腕など)に貼り、48〜72時間後に反応を確認します。
チタンやニッケルなどの金属アレルギーの有無を調べる際にも使われます。
【注意点】
手軽で広く行われている検査です。ただし、金属イオンが皮膚に届きにくい場合は陰性でもアレルギー反応が出ることもあります。
・血液検査
血液検査による金属アレルギー検査は、血液中の免疫細胞が金属に対してどのように反応するかを調べる方法です。
チタンをはじめ、ニッケル・クロム・コバルトなど、複数の金属に対する反応を同時に評価できます。
皮膚に貼るパッチテストでは反応が出にくいチタンや貴金属などのアレルギーをより的確に評価するために行われます。
皮膚が弱い方や、より感度の高い検査を希望する場合にも有効です。
【注意点】
精度が高く、皮膚に貼る必要がないメリットがあるため、皮膚の弱い方の負担を軽減できます。
ただし実施できる施設が限られ、保険適用外の場合が多いでしょう。
・検査の実施例
最近では、インプラント専門クリニックでも治療前にチタンアレルギー検査を導入するケースが増えています。
多くの医院では、パッチテストや血液検査を希望制で案内しており、患者さんの体質に合わせた素材選択が行われています。
検査結果の見方と注意点
陽性 反応あり チタンを使う治療や合金使用は慎重に検討
陰性 反応なし 安全性が高いが、100%安全とは言えない
偽陰性・偽陽性の可能性 金属イオンの透過性、試薬組成などに左右される
被験金属が純粋でない場合、成分の混入などにより予期しない反応が出る可能性もあります。
そのため、検査結果だけで決めるのではなく、臨床判断(症状、有病歴、リスク管理)を併用することが重要です。
ジルコニアインプラント

金属アレルギーのリスクを避けたい方や、すでに金属アレルギーが疑われる方にとって、有力な選択肢のひとつがジルコニアインプラントです。
ジルコニアはセラミックの一種で、奥歯の被せ物にも使用されています。
金属を一切含まない素材で、「メタルフリーインプラント」とも呼ばれます。
ジルコニアのメリット
・体にやさしいメタルフリー素材
金属を含まないため、金属アレルギーを防ぐことが可能です。
・審美性(見た目)
ジルコニアは白く自然な半透明感があり、歯ぐきが下がった場合でも金属のような黒ずみが目立ちにくいのが特徴です。
・高い耐腐食性と安定性
金属のように腐食やイオン溶出が起こらないため、長期間にわたって安定した状態を維持できます。
・プラーク(歯垢)が付きにくい
表面がつるつるしているため、プラークの付着が少なく、インプラント周囲炎のリスクを軽減します。
ジルコニアインプラントの注意点
・強度・耐久性
金属と比べると破折のリスクが少し高いとされており、特に強い力がかかる奥歯などでは慎重な設計が必要です。
・接合部や部品の一部に金属を使用することもある
あごの骨に埋め込むインプラント体はジルコニアで金属を一切使用しない場合でも、土台の部分などに金属が使用される場合があり、完全にメタルフリーとは言い切れないことがあります。
・費用
一般的にチタン製インプラントよりも費用が高い傾向にあります。
・歴史が浅い
チタンに比べると臨床データや長期的なエビデンスがまだ少ないため、長期間の経過がはっきり分かっていない点も課題です。
チタンとジルコニアの比較
チタン製とジルコニア製インプラントの金属アレルギーリスクの違いを下記のように比較しました。
・チタン製インプラント
様々な医科の分野でも使用されており、生体親和性が高く、アレルギーのリスクは低いですが、可能性はゼロではないでしょう。
・ジルコニア製インプラント
金属を含まないため、金属アレルギーの心配がほとんどありません。
そのため、金属アレルギーの可能性をできるだけ減らしたい方はジルコニア製のインプラントが有力な選択肢といえます。
インプラント治療を検討する際の注意点と選び方
インプラント治療をする歯科医院を検討する際、特に金属アレルギーが心配な方は、以下のポイントを意識して選択・相談を行うことが大切です。

- 1 問診と既往歴の共有
金属アレルギーの有無やアレルギー体質、金属接触皮膚炎などの既往は、必ず歯科医師に伝えましょう。
特にピアスやネックレスなどのアクセサリーでかぶれた経験や、義歯や詰め物でアレルギー反応を起こしたことがある方は注意が必要です。
- 2 金属アレルギー検査の実施
可能であれば、治療前にパッチテストや血液検査を受けて、金属アレルギーの有無を確認しておきましょう。
そうすると、リスクを事前に把握し、適切な素材を選ぶ判断材料になります。
ただし、検査結果はあくまで参考情報の一つとして、最終判断はお口の状況を考慮して、歯科医師と相談のうえで行うことが大切です。
- 3 使用素材の確認と選択肢の提示
治療計画の段階で、使用するインプラント素材(純チタン、チタン合金、ジルコニアなど)を提示してくれる歯科医院を選びましょう。
素材の違いや特徴を説明し、患者様が選択できる体制のある医院が安心です。
- 4 メタルフリー・ハイブリッド設計の検討
金属を一切使用しないジルコニアインプラント(メタルフリー設計)や、アバットメントや上部構造のみ非金属素材を用いるハイブリッド設計も選択肢として検討できます。
- 5 手術器具による金属接触への配慮
インプラント手術では、ドリルやピンなどの金属製器具を使用します。
金属アレルギーの可能性が高い場合は、器具の材質や表面処理、滅菌方法などの管理体制についても確認しておくと安心です。
- 6 治療後の定期チェックと経過観察
手術後は、口の中や皮膚の変化(口腔扁平苔癬、発疹、掌蹠膿疱症など)を定期的に確認しましょう。
違和感や症状が出た場合は、早めに受診して原因を特定することが大切です。
- 7 異常が出た場合の対応
万が一アレルギー症状が明らかになった場合は、チタンインプラントを撤去してジルコニアへ交換するという選択も考えられます。
ただし、撤去には骨や歯ぐきへの負担・費用が伴うため、あらかじめリスクを十分に把握しておくことが大切です。
インプラントと金属アレルギーの関係を症例から解説
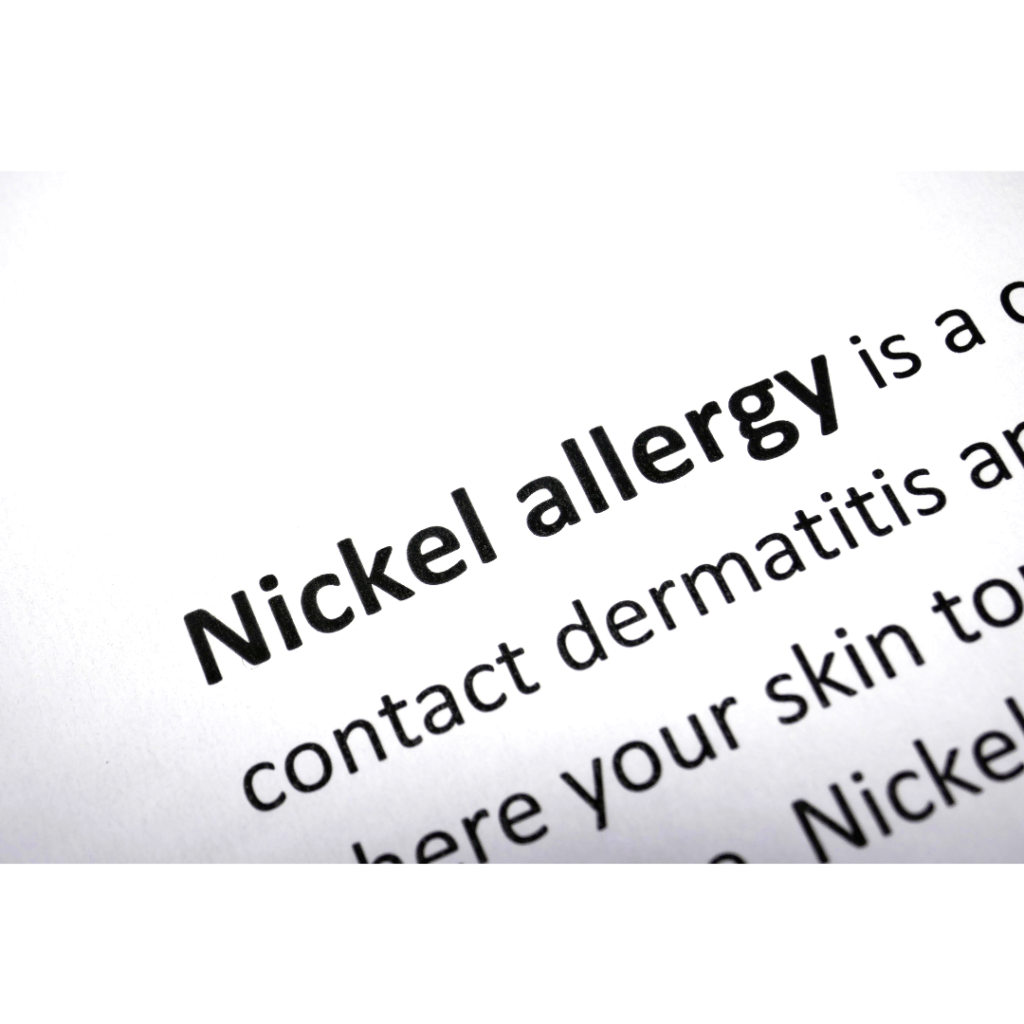
実際に報告されている症例をもとに、インプラントと金属アレルギーの関係を具体的にご紹介します。
口腔扁平苔癬の発症例
インプラント埋入後に口腔内へ白いレース状の病変(苔癬状斑)が出現し、口腔扁平苔癬と診断されたケースが報告されています。
原因として、金属イオンとタンパク質が結合して形成される複合体によるⅣ型(遅延型)アレルギー反応が疑われ、インプラント撤去後に症状が改善したとされています。
掌蹠膿疱症の悪化例
掌蹠膿疱症を持つ患者がインプラント治療を受けた後に、皮膚症状が悪化した症例も報告されています。
このケースでは、歯科用金属やインプラントの撤去によって膿疱症状が改善したとされており、金属との関連があると考えられています。
インプラントと金属アレルギーとの可能性を完全に否定することはできません。
とくに皮膚疾患の既往がある方やアレルギー体質の方は、事前に検査を受け、使用する素材を慎重に選ぶことが大切です。
治療前に確認したい金属アレルギー対策のポイント

チタンは金属の中でもアレルギーリスクが低く、現在のインプラント治療で広く一般的に使用されている素材です。
ただし、チタンアレルギーはまれなケースではありますが、起こり得るとされており、実際に遅延型アレルギーとして報告された症例もあります。
チタンアレルギーが疑われる場合には検査を行い、アレルギーの有無を確認することをおすすめします。
金属アレルギーのリスクを避けたい方には、ジルコニアインプラント(メタルフリー素材)が有力な選択肢となります。
当院では数多くのインプランと治療を行っているため、インプラントの疑問や不安がある場合もお気軽にご相談ください。


